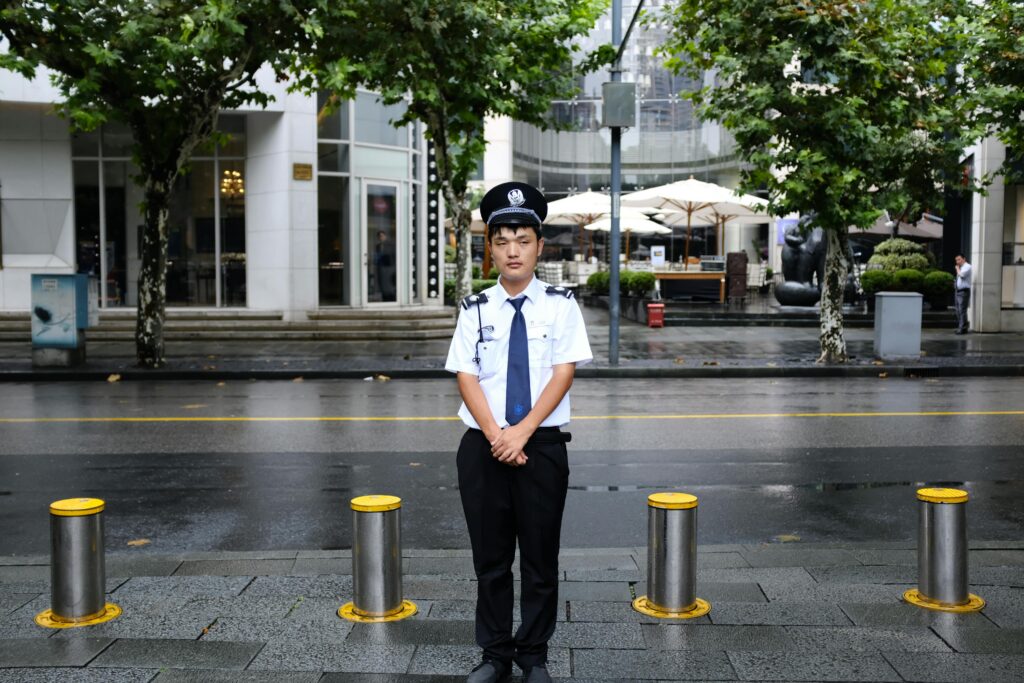警備員には、防犯や防災に関する専門的な知識と技術が求められます。さらに、資格を取得することで視野が広がり、緊急時にも冷静に対応できる力が身につきます。施設警備2級は初心者でも挑戦しやすい資格のため、積極的に取得することをおすすめします。ここでは、施設警備2級の概要について詳しくご紹介します。
施設警備業務検定2級とは
施設警備業務検定2級は、未経験者でも挑戦できる国家資格です。警備会社で働く多くの方が取得しており、直接受験で合格するか、特別講習を受けてから試験に合格することで資格を得られます。ここでは、合格率や資格取得後にできる業務について詳しく解説します。合格率・直接受験について
直接受験の場合、合格基準は9割以上と厳しく、合格率は約20~40%です。学科試験と実技試験がそれぞれ年に1回実施されます。合格までに十分な学習時間が必要ですが、受験料は1万6,000円(税込)と比較的リーズナブルなのがメリットです。時間をかけてじっくり学べる方に向いています。合格率・特別講習受験について
特別講習を受けた後に試験を受ける方法で、18歳以上で警備員新任教育を30時間受講した方が対象です。合格率は60~80%と高く、初心者にとって非常に取得しやすい方法です。初心者は6日間、経験者は2日間の講習を登録講習機関で受けます。集中して学べるため実力が身につきやすく、効率的に資格取得を目指せます。費用は初心者が79,200円(税込)、経験者は33,000円(税込)ですが、会社負担となる場合もあるため相談してみましょう。
施設警備業務検定2級を取得するとできること
この資格は、将来的なキャリアアップにも役立ちます。取得後1年以上施設警備に従事すると、上位資格である施設警備業務検定1級の受験資格が得られます。また、資格手当や昇進の対象になることも多いです。空港や核燃料物質取扱施設など重要な施設での警備業務にも従事でき、法律上、施設警備業務検定1級・2級保有者の配置が義務付けられています。
資格を取得することで、貴重な経験を積み、同じ業界内での転職時にも有利になるでしょう。施設警備業務検定2級は、警備員としてスキルアップを目指す方に必須の資格です。
施設警備業務検定2級の試験内容
施設警備業務検定2級の取得には、多くの学習時間や講習の受講が必要です。試験は学科試験と実技試験に分かれているため、両方をバランスよく対策することが重要です。学科試験は以下の4科目から構成されています。・警備業法
・関係法令
・破壊や事故時の応急措置
・基礎業務
特別講習を受けると、それぞれの科目をより詳しく学べるため、理解が深まります。試験では過去問を基にした出題が多いため、過去問対策は必須です。公式テキストと過去問を繰り返し使い、苦手分野を重点的に克服しましょう。
また、複数年分の過去問を分析することで、出題傾向を把握できます。頻出項目を優先的に学ぶことで、効率的に得点アップが狙えます。
施設警備業務検定2級の実技試験って何をするの?
学科試験合格後、別日に実技試験が行われます。評価項目が多いため、一つひとつ丁寧に練習し、正確さを高めることが重要です。ここでは、実技試験の内容と効果的な対策をご紹介します。実技試験の内容
実技試験の科目数は、直接受験が9項目、特別講習受講の場合は6項目です。主な試験内容は以下の通りです。・出入管理(手荷物検査や金属探知機の操作)
・自動火災報知機(自火報)の確認と操作
・警察機関への連絡(犯罪や火災を想定した対応)
・負傷者の搬送(回復体位の処置や意識不明者の搬送)
・警戒杖の基本操作(立杖、休め、常の構え、本手打ち、逆手打ちなど)
・巡回の実施(正しい手順や必要項目の説明)
出入管理では、手荷物検査や金属探知機の扱いが評価されます。自火報の操作は、正確な確認と的確な対応が求められます。警察への連絡は、状況想定文を記憶し、適切に答える必要があります。
負傷者の搬送では、回復体位の取り方や動けない方への対応がポイントです。警戒杖の操作は、教本を使ってしっかり練習しましょう。巡回では、決められた流れや確認項目を説明できることが求められます。